【大阪市】腰椎すべり症の痛み・痺れ|手術しかないと諦める前に
こんにちは。大阪市の浜崎鍼灸整骨院、院長の浜崎です。
「先生、10分も立っていると足が痺れてくるんです」「孫の運動会で、写真を撮ってやれなかったのが辛くて…」 最近、働き盛りの方から、このような腰椎すべり症の切実な相談が特に増えています。
患者さまが訴える具体的な悩みは、「病院では痛み止めとコルセットを渡され、『悪化すれば手術しかない』と言われた」「整骨院のマッサージもその場しのぎで、根本的に治る気がしない」といった、先の見えない不安を伴うものがほとんどです。
病院では原因が分かっていても、治療を受けてもなかなか改善せずに、好きな趣味や大切な家族との時間まで諦めかけている。きっと他にも同じように、もどかしい思いを抱えながら一人で苦しんでいる方がいるはずだ。 その方たちの「伴走者」として、手術以外の、根本改善への道筋を示したい。その一心で、この記事を書きました。

こんなお悩みはありませんか?
- 長時間立っていたり、歩いたりすると腰から足にかけて痛みや痺れが出る
- 朝、顔を洗う時など、前かがみの姿勢が辛い
- 腰を反らすと痛みが強くなる
- 病院で腰椎すべり症と診断され、手術を勧められたが、できれば避けたい
- 痛み止めや湿布でごまかしているが、根本的に治したい
- このままでは仕事や趣味を続けられないのではないかと不安だ
- マッサージや整体に通ったが、効果が一時的だった

そもそも腰椎すべり症とは?

腰椎すべり症とは、積み木のように連なっている腰の骨(腰椎)が、文字通り前方に「すべって」しまい、正常な位置からずれてしまう症状です。
骨がずれることで、その近くを通る神経が圧迫されたり、引っ張られたりします。これにより、腰の痛みだけでなく、お尻から太もも、ふくらはぎ、足先にかけての痛みや痺れ(坐骨神経痛のような症状)を引き起こします。
特に、長時間立っている、歩く、腰を反らすといった動作で症状が悪化しやすいのが特徴です。初期は腰の重だるさ程度でも、進行すると歩行が困難になるなど、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。
(参考:公益社団法人 日本整形外科学会)
腰椎すべり症の一般的な原因

なぜ、腰の骨がすべってしまうのでしょうか。一般的には、以下のような原因が挙げられます。
- 加齢による椎間板や関節の変性: 年齢と共に、骨と骨の間でクッションの役割を果たす椎間板や、関節が変性してもろくなり、腰椎を支える力が弱まることで発症します(変性すべり症)。中高年の女性に多く見られます。
- 分離症からの移行: 若い頃のスポーツなどで腰に繰り返し負担がかかり、腰椎の一部が疲労骨折(腰椎分離症)を起こし、その部分が不安定になってすべってしまうことがあります(分離すべり症)。
- 長時間の不良姿勢: デスクワークや立ち仕事などで、腰に負担のかかる姿勢を長時間続けることも、腰椎の不安定性を助長する一因となります。
しかし、これらはあくまで一般的な原因です。同じような年齢や生活習慣でも、症状が出る人と出ない人がいるのはなぜでしょうか。本当の原因は、骨のずれそのものだけではないのです。
実際、腰椎のずれがあっても症状が出ない方もいる一方で、軽度のすべりでも強い痛みや痺れを訴える方もいます。これは、骨の位置異常だけでなく、周囲の筋肉の過緊張や血流の滞り、自律神経の乱れなどが複合的に関与しているためです。
鍼灸や徒手療法では、こうした「機能的な問題」に着目し、神経や筋肉のバランスを整えることで症状の改善を図るアプローチが確立されています。整形外科的な画像診断だけでは捉えきれない部分にこそ、根本改善のヒントが隠れているのです。

この症状を放置するとどうなるか
「歳だから仕方ない」「いつもの痛みだ」と腰椎すべり症を放置してしまうと、症状は着実に進行していく可能性があります。
最初は時々感じる程度だった痛みや痺れが、次第に常態化し、歩ける時間がどんどん短くなっていきます。神経の圧迫が長期間続くと、足の感覚が鈍くなったり、足に力が入らなくなったり(筋力低下)、排尿や排便に問題が生じる「膀胱直腸障害」に至るケースもあります。
何よりも辛いのは、痛みや痺れへの恐怖から、旅行や趣味、友人との集まりといった、人生の楽しみを一つ、また一つと諦めていかなければならないことです。腰椎すべり症の放置は、あなたの活動範囲と可能性を、少しずつ狭めていってしまうのです。
病院での一般的な対処法

腰椎すべり症で整形外科を受診した場合、一般的には以下のような対処法が取られます。
- 保存療法: まずは手術以外の方法で症状の緩和を目指します。
- 薬物療法: 痛み止め(非ステロイド性抗炎症薬)や、神経の痛みを和らげる薬、血流を改善する薬などが処方されます。
- 装具療法: コルセットを装着し、腰椎を安定させて負担を軽減します。
- リハビリテーション: 腹筋や背筋を鍛える体操や、ストレッチを行い、腰椎の安定化を図ります。
- 神経ブロック注射: 痛みが非常に強い場合、神経の周りに局所麻酔薬を注射し、一時的に痛みを遮断します。
- 手術療法: 保存療法で改善が見られない場合や、歩行困難、麻痺などの症状が進行した場合には、神経の圧迫を取り除くための手術が検討されます。
これらの治療は有効な選択肢ですが、薬や注射はあくまで一時的な痛みの緩和であり、手術は体に大きな負担をかけます。多くの方が「手術は最後の手段にしたい」と考えるのは当然のことです。
(参考:日本脊椎脊髄病学会)

なぜ当院では根本改善が可能なのか
病院で「手術しかない」と言われたり、治療を続けても改善しなかったりするのは、すべっている骨だけを問題視しているからです。私は、症状だけを診る「修理屋」ではなく、患者さまの人生の「伴走者」でありたいと考えています。
私の治療家としての原点は、トップアスリートを見ていたトレーナー時代にあります。彼らにとって治療は最優先。しかし、一般の方々は違います。仕事があり、家庭があり、生活がある。その中で「なぜ腰椎がすべり、神経を圧迫するに至ったのか」という本当の原因は、一人ひとり全く違うのです。
当院では、以下の6つの理由から、あなただけの腰椎すべり症の根本原因を見つけ出し、手術に頼らない改善へと導くことができます。
- 1. 担当者固定制
- 毎回同じ施術者が担当することで、あなたの体の小さな変化や、生活の中での気づきも見逃しません。一貫した視点で、常に最適な施術とアドバイスを提供します。
- 2. 多角的な検査
- 姿勢解析や自律神経チェックソフト、そして専門家による徒手検査を組み合わせ、痛みの原因を多角的に分析。なぜ腰椎に負担がかかっているのか、その根本原因を明らかにします。
- 3. あなただけの「施術計画書」
- 検査結果と豊富な臨床データに基づき、あなたの目標達成に向けたオーダーメイドの施術計画を作成します。ゴールが明確になることで、安心して治療に専念できます。
- 4. 独自の「インナーマッスル・トリートメント」
- 鍼灸やオステオパシーなどを統合した、体への負担が少ない独自の施術です。腰だけでなく、腰椎を支えるお腹周りの深層筋(インナーマッスル)や、骨盤、股関節など、体全体を整え、腰に負担のかからない体づくりを目指します。
- 5. 4つの国家資格
- 解剖学や生理学など、国が定める厳しい基準をクリアした国家資格者が、医学的知識に基づいた安全で効果的な施術をお約束します。
- 6. 地域No.1クラスの高い評価
- 大手口コミサイトなどで、実際に症状が改善された多くの患者さまからお喜びの声をいただいています。これが、私たちの施術が信頼できる何よりの証です。

実際に腰椎すべり症を克服された方々の喜びの声
「手術を回避でき、孫を追いかけられるようになりました」(50代 男性 工場勤務) 5年以上、腰椎すべり症の痛みと痺れに悩み、病院では手術しかないと言われていました。藁にもすがる思いでこちらを選んだのは、「伴走者」という先生の言葉に惹かれたからです。先生は私の「孫の写真を撮りたい」という想いを真剣に受け止め、施術計画を立ててくれました。今では痛みなく歩けるようになり、この前の運動会では最高の笑顔を撮ることができました。
「立ち仕事の恐怖がなくなりました」(40代 女性 販売員) 長時間立っていると足が痺れてきて、仕事に集中できないのが悩みでした。当院の多角的な検査で、原因が腰だけでなく、股関節の硬さにもあると分かり、目から鱗でした。施術を受けるたびに体が軽くなり、今では一日中立っていても平気です。担当の先生がずっと同じなので、些細なことも相談しやすかったのが良かったです。
「薬を手放せました」(60代 女性 主婦) 毎日のように痛み止めを飲んでいましたが、胃が荒れるのが心配でした。先生の施術はとてもソフトで、鍼もほとんど痛みを感じません。治療だけでなく、家でできる簡単な体操も教えていただき、実践するうちに薬を飲む回数がどんどん減っていきました。今では薬なしで生活できており、本当に感謝しています。
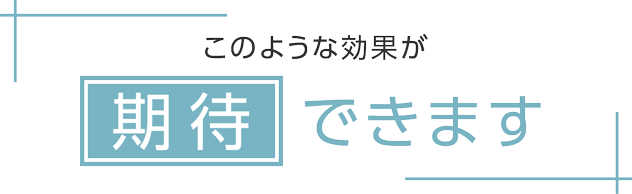
腰椎すべり症が改善した場合の未来

想像してみてください。 足の痺れを気にすることなく、好きなだけ散歩や買い物を楽しめる毎日を。 腰の痛みに邪魔されず、仕事に集中し、週末には趣味のカメラを手に、大切な家族との時間を満喫しているあなたの姿を。
「もう無理かもしれない」と諦めかけていた旅行や、孫と遊ぶ約束。それらを、心からの笑顔で実現できる。痛みがなくなるだけでなく、あなたの人生そのものが、よりアクティブで彩り豊かになる。 それが、当院が目指す根本改善の先にある未来です。
自宅でできる簡単セルフケア

改善を早め、再発を防ぐために、ご自宅でできる簡単なセルフケアを2つご紹介します。腰椎すべり症の方は、腰を反らす動きは避けるべきです。痛みを感じる場合は、絶対に無理をしないでください。
1. ドローイン(腹式呼吸)
これは、腰椎を支える天然のコルセットである「腹横筋」を鍛える、最も基本的で重要な運動です。
- 仰向けに寝て、膝を立てます。
- 鼻からゆっくり息を吸い込み、お腹を大きく膨らせます。
- 次に、口からゆっくりと息を吐きながら、お腹をへこませていきます。この時、おへそを背骨に近づけるようなイメージで行います。
- 息を吐ききって、お腹が薄くなった状態を10~30秒キープします。呼吸は止めないようにしましょう。
- これを5~10回繰り返します。
2. 膝抱えストレッチ
硬くなりがちな腰やお尻の筋肉を、安全に伸ばすストレッチです。
- 仰向けに寝ます。
- 片方の膝を両手で抱え、胸にゆっくりと引き寄せます。
- 腰からお尻にかけての筋肉が心地よく伸びるのを感じながら、20~30秒キープします。
- 反対側の足も同様に行います。
- 最後に、両膝を抱えて同様に行います。
腰椎すべり症FAQ

- 腰椎すべり症は、放っておいても自然に治りますか?
-
残念ながら、一度すべってしまった骨が自然に元の位置に戻ることはありません。そのため、放置すれば加齢と共に腰椎の不安定性は増し、症状が徐々に進行していく可能性が高いです。痛みや痺れは、体が発している危険信号です。「そのうち治る」と過信せず、症状が軽いうちに適切なケアを始め、進行を食い止めることが何よりも重要です。
- 腰椎すべり症の人が、絶対にやってはいけないことは何ですか?
-
最もやってはいけないのは、腰を強く反らす動きです。腰椎のすべりを助長し、神経の圧迫を強めてしまうため、非常に危険です。例えば、うつ伏せで本を読む、ゴルフのスイングで過度に腰を反る、といった動きは避けるべきです。また、重いものを持ち上げる際は、膝をしっかり曲げて腰を落とし、腰だけで持ち上げないように注意してください。
- 手術しかないと言われましたが、本当に改善の見込みはありますか?
-
はい、多くの場合、改善の見込みは十分にあります。なぜなら、痛みや痺れの直接的な原因は、骨のすべりそのものよりも、それによって引き起こされる筋肉の過緊張や血行不良、神経の興奮にあることが多いからです。当院の鍼灸や独自の施術は、これらの問題に的確にアプローチし、神経の圧迫を和らげることができます。手術は最後の手段と考える前に、ぜひ一度ご相談ください。
- この痺れは、本当に取れるのでしょうか?
-
その不安、とてもよく分かります。神経症状の改善には時間がかかることが多く、症状の改善には個人差がありますが、諦める必要はありません。痺れの原因である神経の圧迫や血行不良を、鍼灸などで改善していくことで、痺れの範囲が狭まったり、頻度が減ったりと、多くの方が変化を実感されています。私たちはあなたの「伴走者」として、そのわずかな変化も見逃さず、一緒に改善を目指します。
- コルセットは、ずっと着けていた方が良いですか?
-
痛みが非常に強い急性期には、コルセットで腰を安定させることは有効です。しかし、長期間頼りすぎると、腰を支える自分自身の筋肉(インナーマッスル)が弱ってしまい、かえって腰椎を不安定にさせてしまう可能性があります。当院では、コルセットに頼らなくても良い体づくりを目指し、あなた自身の筋力を取り戻すサポートをしていきます。
腰椎すべり症の根本改善へ|最後に覚えておきたいポイント
- 腰椎すべり症の痛みや痺れは、骨のずれだけでなく、筋肉の緊張や血行不良が大きく関係しています。
- 病院の治療で改善しないのは、痛みの根本原因である「なぜ腰に負担がかかっているのか」が解決していないためです。
- 放置すると症状が進行し、歩行困難や手術のリスクが高まるため、早期の対処が重要です。
- 腰を強く反らす動きは、症状を悪化させるため絶対に避けるべきです。
- 当院では、多角的な検査であなただけの原因を特定し、オーダーメイドの施術計画で根本改善を目指します。
- 鍼灸を含む独自の施術で体全体のバランスを整え、手術に頼らない、再発しない体づくりをサポートします。
- 私たちのゴールは痛みの解消だけでなく、あなたが不安なく趣味や日常生活を楽しめる未来を取り戻すことです。
この記事の執筆者
- 院名: 浜崎鍼灸整骨院
- 役職: 院長
- 年齢: 57歳
- 所在地: 大阪市
- 保有国家資格: 鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師
- メディア実績等: 24時間テレビ「愛は地球を救う」チャリティーマラソンにメディカルスタッフとして参加。新聞・テレビなど取材多数。国内だけでなく海外からも患者が来院。
- 人物像: 三児の父。趣味はラグビー、ソフトボール、ハイキング、サイクリング、映画・音楽鑑賞、食事会。地域で町会長としてボランティア活動にも積極的で、災害ボランティア経験もあり。
- モットー: 「やり過ぎない」
参考:公益社団法人 日本整形外科学会, 日本脊椎脊髄病学会


